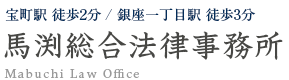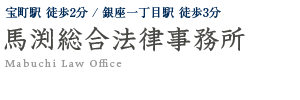賃貸借と改正民法③ 個人保証の限度額
2017-11-24
賃貸借契約とオーナーと賃借人の間で締結する場合、通常、連帯保証人をつけることになります。
連帯保証人は、賃料の不払いや、賃借物を賃借人が損傷させた場合の損害賠償債務まで、連帯して責任を負うことになり、これまで連帯保証人の責任が重くなりすぎる点が問題になっていました。
そこで、改正民法においては、個人の根保証契約は、極度額を定めなければ、効力を生じないと規定されています(改正民法465条の2第1項、第2項)。
オーナー側としても、個人の方に連帯保証をしてもらう場合には、保証の限度額を定めるようにしましょう。
限度額を定めない場合には、連帯保証契約自体が無効となってしまうため、注意が必要です。
なお、極度額を定めなければ無効となるのは、あくまでも個人の方が連帯保証を行う場合です。
法人が連帯保証を行う場合には、当該規制は及びません。

東京都中央区銀座の「馬渕総合法律事務所」は、企業法務から不動産、労働問題、債権回収、破産など幅広い分野に対応しています。
迅速かつ的確なアドバイスで、ビジネスにおける「安心」をご提供。
東京、神奈川、埼玉、千葉を中心に、日本全国からのご相談もオンラインで承ります。
お客様のビジネスに寄り添い、法的なリスク管理と成長をサポートするパートナーとして、誠実に対応します。
まずはお気軽にお問い合わせください。
←「賃貸借と改正民法② 敷金の定義と原状回復義務の範囲」前の記事へ 次の記事へ「賃貸借と改正民法④ 賃借人による修繕」→