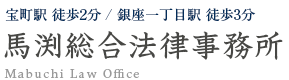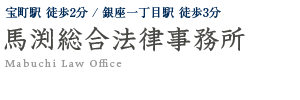Archive for the ‘未分類’ Category
株式会社における重要な業務執行の決定
会社の機関設計において、監査役会設置会社を採用した場合、取締役会を設置しなければなりません(会社法327条1項2号)。
そして、取締役会設置会社においては、取締役会において重要な業務執行の決定をする必要があります。
重要な業務執行の決定については取締役に委任することはできません(会社法362条4項)。
従って、監査役会設置会社は、取締役会に上程する議題が多くなるという問題が生じています。
また、何が「重要な業務執行」に該当するのか、一義的な基準がないため、基準を明確にすべきとの議論が従前から上がっています。
以下、平成29年8月28日付日本経済新聞より、引用。
「監査役会を置く企業で不満が多いのは、取締役会に上程する付議事項の多さだ。監査役を置かない委員会型の企業では、業務執行を担う役員などへの大幅な権限委譲が可能で、取締役会は監督機能に徹することが容易。ところが監査役会設置会社では会社法上、取締役会が重要な業務執行の決定をしなければならず、権限委譲は限定的だ。企業法務の専門家の間では、何が「重要な業務執行」にあたるのか、その線引きについて議論されてきた。「総資産の100分の1程度でも重要業務になりうるとした最高裁判例があり、この数字が実務で定着したが明確な基準はない」(東京大学の田中亘教授)
国際競争が激しくなるなか「しゃくし定規の解釈は機動的な業務執行の妨げになる」として基準の明確化や法文の見直しを求める向きもある。次の会社法改正案を話し合う法制審議会(法相の諮問機関)でもテーマに浮上している。「制度間競争を実現するため、機関設計(統治モデル)にかかわらず同一の基準を認めるべきだ」との意見と、「監査役会設置会社が委員会型に移行すれば足りる」と現状維持を求める意見の賛否両論があり、着地点はまだ見えない。」

東京都中央区銀座の「馬渕総合法律事務所」は、企業法務から不動産、労働問題、債権回収、破産など幅広い分野に対応しています。
迅速かつ的確なアドバイスで、ビジネスにおける「安心」をご提供。
東京、神奈川、埼玉、千葉を中心に、日本全国からのご相談もオンラインで承ります。
お客様のビジネスに寄り添い、法的なリスク管理と成長をサポートするパートナーとして、誠実に対応します。
まずはお気軽にお問い合わせください。
違法残業と社名公表
長時間の違法残業を行っていた会社について、新基準に基づき、実会社名が公表されました。
違法残業の背景には、労働者不足があるようですが、今後、ますまず違法残業への規制は強化されていくものと考えられます。
労働者保護に加え、違法残業、公表による企業価値の毀損を回避するためにも、今後の労務管理が重要課題となります。
以下、平成29年9月5日付日本経済新聞より、引用。
「厚生労働省愛知労働局は4日、複数の事業所での違法な長時間労働で是正指導したにもかかわらず、その後も改善しなかったとして、名古屋市の運送会社「大宝運輸」の社名を公表し再度、是正指導した。月80時間を超す違法な時間外・休日労働が同社のトラック運転手の約2割、計84人で確認された。うち74人は月100時間超で、最長197時間のケースもあった。
厚生労働省は今年1月、電通の新入社員の過労自殺問題を受け、違法な残業をさせた企業の社名公表基準を拡大。従来は従業員10人以上で月100時間超の残業が確認さた場合などを対象にしていたが、「月80時間超」などに厳格化した。基準拡大後、社名公表は同社が初めて。」

東京都中央区銀座の「馬渕総合法律事務所」は、企業法務から不動産、労働問題、債権回収、破産など幅広い分野に対応しています。
迅速かつ的確なアドバイスで、ビジネスにおける「安心」をご提供。
東京、神奈川、埼玉、千葉を中心に、日本全国からのご相談もオンラインで承ります。
お客様のビジネスに寄り添い、法的なリスク管理と成長をサポートするパートナーとして、誠実に対応します。
まずはお気軽にお問い合わせください。
アパート融資について
少し前のニュースになりますが、アパート融資の残高が平成2016年12月末時点で22兆166億円となり、過去最高を更新したようです(前年同月比4.9%増)。
相続税対策の一環として、①所有地にアパートを建てることで土地の評価額を下げ、②銀行からの融資は債務となるため、遺産総額を圧縮できることがメリットとなります。
アパートを建築した後に、一括で借り上げて転貸する「サブリース」と呼ばれる建築請負業者が家賃保証をするケースが多いですが、昨今、家賃保証の範囲をめぐって、紛争に発展するケースが多くなっています。
以下、2017年4月23日付日本経済新聞より、引用。
「アパート融資 賃貸アパートの建築資金をまかなうための融資。日銀によると2016年12月末の融資残高は前年同月比4.9%増の22兆1668億円で09年の統計開始以来、過去最高を更新した。新規の融資先を見つけにくいなかで、銀行もアパート融資に力を入れている。
15年の相続税制の改正で課税対象が拡大し、これまで相続税を払う必要がなかった層が新たに含まれることになった。所有地にアパートを建てると土地の評価額を下げることができるほか、銀行からの融資は債務となるため財産額を圧縮できる。こうした節税効果に資産家らが着目し、短期間で需要が急増した。
アパートを建築した後に一括で借り上げて転貸する「サブリース」と呼ばれる建築請負業者が家賃を保証するケースが多い。ただ新築物件との競争が激しく、年数が経過すると空室率が上がり、保証額は逆に下がる。このため金融庁は単に資金需要に応じるのではなく、将来の賃貸アパート需要や空室・賃料低下のリスクを適切に評価し、顧客に説明するよう求めている。」

東京都中央区銀座の「馬渕総合法律事務所」は、企業法務から不動産、労働問題、債権回収、破産など幅広い分野に対応しています。
迅速かつ的確なアドバイスで、ビジネスにおける「安心」をご提供。
東京、神奈川、埼玉、千葉を中心に、日本全国からのご相談もオンラインで承ります。
お客様のビジネスに寄り添い、法的なリスク管理と成長をサポートするパートナーとして、誠実に対応します。
まずはお気軽にお問い合わせください。
残業時間の上限規制 繁忙期は100時間未満
残業時間の上限規制の導入について、これまで労使及び政府で議論がなされてきましたが、労使協定を結べば年間720時間、月平均60時間までが認められることになりました。
繁忙期については、例外として認める残業を100時間未満とすることが固まりました。
年内にも、労働基準法改正案等が国会に提出され、2019年度の運用開始を目指すことになるようです。
これまで、36協定を結べば、1カ月45時間の上限で残業が認められていましたが、更に、「特別条項付きの36協定」を結べば、限度時間を超える時間を延長時間とすることができ、当該い特別条項を設けることで、日常的に限度時間を超える時間外労働を行わせている会社が多くありました。
今回、残業時間の上限規制が導入されることになったのは、意義深いものと思います。
ただし、当該基準時間の妥当性については、賛否が分かれており、過労死の危険性との関係から、当該規制導入後も引き続き、当該基準の妥当性についての検討が必要と考えられます。
以下、平成29年3月14日付日本経済新聞より、引用。
政府が進める働き方改革の柱である残業時間の上限規制を巡り、繁忙月に例外として認める残業を「100時間未満」とすることが固まった。安倍晋三首相が13日、首相官邸で経団連の榊原定征会長、連合の神津里季生会長と会談して要請。労使ともに受け入れる方針で、政府は月内に非正規の待遇改善策なども盛り込んだ実行計画を策定する。
両会長は13日、首相との会談に先立ち、残業時間の上限規制に関する合意文書を作成。時間外労働の上限は労使協定を結べば年間720時間、月平均60時間まで認める。焦点の繁忙月の上限については「100時間を基準とする」との表現を盛り込んだ。
首相は両会長との会談で「ぜひ100時間未満とする方向で検討いただきたい」と要請。榊原会長は会議後、記者団に「首相の要請を重く受け止め、経済界として対応を決めたい」と表明し、神津会長も「労基法70年の歴史の中で非常に大きな改革だ」と語り、労使ともに受け入れる方針を事実上示した。
17日に開く働き方会議では政労使の合意として「100時間未満」が提示される見通しだ。年内に労働基準法改正案などを国会に提出し、2019年度の運用開始を目指す。
労使合意には終業から始業までに一定の休息を設ける「勤務間インターバル制度」導入を法律に盛り込むことも明記。残業規制導入から5年経過後、過労死の労災認定状況などを踏まえ、上限を見直す。現在は適用除外となっている建設や運輸などの業種は運用までの猶予を設けることで政府と経済界は調整する。

東京都中央区銀座の「馬渕総合法律事務所」は、企業法務から不動産、労働問題、債権回収、破産など幅広い分野に対応しています。
迅速かつ的確なアドバイスで、ビジネスにおける「安心」をご提供。
東京、神奈川、埼玉、千葉を中心に、日本全国からのご相談もオンラインで承ります。
お客様のビジネスに寄り添い、法的なリスク管理と成長をサポートするパートナーとして、誠実に対応します。
まずはお気軽にお問い合わせください。
転籍無効の判決について(分社化をした上で解雇を行った事案)
分社化により、新会社に転籍した後に解雇された者が、転籍の無効を求めた訴訟に関し、東京地裁において、法律が定める事前の協議が不十分であり、転籍は無効とする旨の判決が下されました。
商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)は、会社は、承継される事業に従事している労働者と、会社分割に伴う労働契約の承継に関し、協議をすることを求めています(同法5条)。そして、協議が行われても、その程度が著しく不十分であれば、当該労働者は、労働契約承継の効力を争うことが可能です(最高裁判所平成22年7月12日判決、労判1010号5頁)。すなわち、分割会社に対して労働契約上の地位の確認の訴えを提起することができ、当該判決も、かかる最高裁判例の考えに基づくものと思われます。
以下、平成29年4月3日付日本経済新聞(朝刊)より、引用。
神奈川県厚木市の男性(54)が転籍の無効を求めた訴訟の判決で、東京地裁(湯川克彦裁判長)は28日、「法律が定める事前の協議が不十分で、転籍は無効」と判断した。
判決などによると、男性は化粧品会社「エイボン・プロダクツ」(東京・新宿)の厚木工場に勤務していたが、同社が2012年に会社分割の手法で同工場を子会社化したことに伴い、約200人とともに転籍した。その後、子会社が解散し、男性は解雇された。
湯川裁判長は判決理由で「会社は会社分割の大まかな説明をしたが、転籍の希望に関する個別の話し合いは不十分だった」と判断した。判例では、会社分割の際に社員との事前の協議が不十分な場合、転籍が無効となり得るとされている。
判決は男性がエイボン社員であることも認め、未払い賃金の支払いを命じた。判決後に記者会見した男性の代理人弁護士は「人員削減を目的とした分社化を防ぐことにつながる判決だ」とした。
同社は「正式な判決文を受け取っていないためコメントは差し控える」としている。

東京都中央区銀座の「馬渕総合法律事務所」は、企業法務から不動産、労働問題、債権回収、破産など幅広い分野に対応しています。
迅速かつ的確なアドバイスで、ビジネスにおける「安心」をご提供。
東京、神奈川、埼玉、千葉を中心に、日本全国からのご相談もオンラインで承ります。
お客様のビジネスに寄り添い、法的なリスク管理と成長をサポートするパートナーとして、誠実に対応します。
まずはお気軽にお問い合わせください。
関西電力における時間外賃金の未払い 約17億円
関西電力における未払いの時間外賃金が、平成28年12月末までの2年間で約17億円に及ぶことが明らかとなりました。
時間外賃金の未払いは、過去2年間に遡って、支払義務が生じます(労働基準法115条)。
関西電力のケースでは、対象者が約1万2000人、未払額が300万円を超えている社員は5名、未払い額は約17億円とされており、会社の経営状況にも多大な影響が及ぶことになりそうです。
時間外労働の未払状況を生じさせないためにも、日々の労働時間管理の強化が必要となります。
以下、平成29年3月30日付日本経済新聞より、引用。
「関西電力は30日、2016年末までの2年間で、全従業員の半数以上にあたる1万2千人に合計で約17億円の時間外賃金を払っていなかったと発表した。関電は同日、労働基準監督署に報告した。」「関電では高浜原発1、2号機(福井県高浜町)の運転延長を巡り、原子力規制委員会の審査対応をしていた課長職の40代男性が昨年4月に自殺。男性はその後労災と認定され、同12月下旬には天満労働基準監督署から適正な労働時間の管理をするよう是正勧告を受けていた。これを受けて同社は今年2月、全従業員約2万2千人の出勤簿やパソコンの使用記録、メールの送信記録などを突き合わせる方法で、昨年12月末までの2年間の勤務実態を調べた。」
「その結果、約1万2900人の計約55万5900時間分の割増賃金や深夜手当など、合わせて約17億円が未払いだったことが判明した。このうち社員5人は未払い額が300万円を超えていたという。」「同社では今年1月、社長を委員長とし、勤務実態の是正を話し合う委員会を設置。朝方や在宅での勤務を積極的に活用することや、深夜の不要不急なメールを原則禁止とするなどの対応策をとりまとめ、同月労基署に報告している。」

東京都中央区銀座の「馬渕総合法律事務所」は、企業法務から不動産、労働問題、債権回収、破産など幅広い分野に対応しています。
迅速かつ的確なアドバイスで、ビジネスにおける「安心」をご提供。
東京、神奈川、埼玉、千葉を中心に、日本全国からのご相談もオンラインで承ります。
お客様のビジネスに寄り添い、法的なリスク管理と成長をサポートするパートナーとして、誠実に対応します。
まずはお気軽にお問い合わせください。
サービス残業の抑制と労働時間の管理
今月、ヤマトHDが未払い残業代を支給する旨のニュースがありました。
労働基準法によると賃金の請求権の消滅時効は2年間とされています(同法115条)。すなわち、現時点より遡って2年間の間に、残業代の未払いがあれば、会社には支払義務が生じます。
一斉に対象社員全員の未払残業代の清算をすることになれば、会社の業務、経営状況に多大な影響を及ぼします。
労働時間の把握、管理は、使用者の責務とされています(平成13年4月6日基発339号「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」)。
サービス残業を抑制し、労働時間を適切に把握するためには、①始業終業の確認はタイムカード、ICカード等の客観的な記録を利用することと、②労務管理を行う責任者を明確に決めておくこと等、労働時間の管理体制の強化が不可欠となります。
以下 平成29年3月4日付日本経済新聞より、引用。
「ヤマトホールディングス(HD)がトラック運転手などのサービス残業の実態を調査し、給料の未払い分を支給する方針であることが分かった。インターネット通販で急増する荷物をこなそうとすることで、現場が混乱をきたし、労働時間を正確に把握する仕組みが機能していなかった。集配拠点の管理職を増やすなどして労働時間の管理体制を厳格化し、再発防止に取り組む。」
「子会社のヤマト運輸のトラック運転手などグループ全体の4割に当たる約7万6000人の従業員を対象に労働時間の聞き取り調査を始めた。3月末をめどに終え、未払い分を順次支給する。」「未払い残業代が100万円を超える従業員もいるとされ、ヤマトHDの支払総額は数百億円に上る可能性がある。」

東京都中央区銀座の「馬渕総合法律事務所」は、企業法務から不動産、労働問題、債権回収、破産など幅広い分野に対応しています。
迅速かつ的確なアドバイスで、ビジネスにおける「安心」をご提供。
東京、神奈川、埼玉、千葉を中心に、日本全国からのご相談もオンラインで承ります。
お客様のビジネスに寄り添い、法的なリスク管理と成長をサポートするパートナーとして、誠実に対応します。
まずはお気軽にお問い合わせください。
債権回収④ 仮差押の有益性
債権者が売掛金や貸付金等の金銭債権を強制的に回収するためには、勝訴判決等の債務名義を取得し、強制執行を行う必要があります。
しかし、これらの手続を待っていては、裁判の間に、債務者が保有財産(不動産や預貯金等)を隠匿・散逸してしまい、勝訴判決が得られても債権回収を実現できないというリスクが生じます。
そのために、債権者は、「強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるとき」には、裁判所に対し、仮差押命令の発令を求めることが可能です(民事保全法20条1項)。
裁判所により、仮差押命令が発令され、当該命令の正本に基づき仮差押が執行されると、債務者による対象財産の処分が禁止され、債権者は、債務者の財産を保全することができます。
仮差押の対象としては、①不動産、②債権、③動産等が考えられます。
また、仮差押の手続により、債務者が反応し、慌てて任意で金銭を支払ってくるというケースもありますので、仮差押は、債権回収を実現する上で、まず検討すべき手法といえるでしょう。

東京都中央区銀座の「馬渕総合法律事務所」は、企業法務から不動産、労働問題、債権回収、破産など幅広い分野に対応しています。
迅速かつ的確なアドバイスで、ビジネスにおける「安心」をご提供。
東京、神奈川、埼玉、千葉を中心に、日本全国からのご相談もオンラインで承ります。
お客様のビジネスに寄り添い、法的なリスク管理と成長をサポートするパートナーとして、誠実に対応します。
まずはお気軽にお問い合わせください。
債権回収③ 取扱金額の範囲について(司法書士と弁護士)
平成28年6月27日、過払金の対応等の債務整理で、借金の金額が140万円を超える場合、司法書士は代理できない旨の最高裁判所の判決が下されました。
司法書士法は、司法書士が訴訟代理人を受任できるのは、請求金額が140万円以下の簡易裁判所の訴訟に限る旨規定していますが、これまで、例えば、200万円の支払いを請求し、和解金額が140万円となる場合等、依頼者が受ける利益が140万円以下となる場合には、司法書士も受任できる旨の解釈のもと、実務の運用がなされてきました。
しかし、同最高裁判決によって、請求金額や債務金額という画一的な基準によって定めるものとされ、受任できる範囲が明確となり、請求金額自体、債務金額自体が140万円を超える場合は、弁護士でないと受任ができなくなりました。
交渉や裁判の結果によって、初めて分かる依頼者が受けた利益を基準とする解釈は避けるべきことが同判断の理由となっています。
(日本経済新聞・平成28年6月27日付)

東京都中央区銀座の「馬渕総合法律事務所」は、企業法務から不動産、労働問題、債権回収、破産など幅広い分野に対応しています。
迅速かつ的確なアドバイスで、ビジネスにおける「安心」をご提供。
東京、神奈川、埼玉、千葉を中心に、日本全国からのご相談もオンラインで承ります。
お客様のビジネスに寄り添い、法的なリスク管理と成長をサポートするパートナーとして、誠実に対応します。
まずはお気軽にお問い合わせください。
債権回収② 三井住友銀行における債務者口座情報の開示
東京弁護士会と株式会社三井住友銀行が協定を締結し、平成28年10月3日より、民事執行法第22条に定める債務名義(ただし、同条5号の執行証書は除く。)に基づく債権差押命令申立事件のため、三井住友銀行本店へ照会することで、口座情報の開示が得られるようになりました。
1 対象事件
債権差押命令申立事件(ただし、相続事件や財産分与事件は対象外です。)
2 回答対象
①預金口座の有無
②口座がある場合は、本支店名、口座科目、科目毎の預金残高
3 照会先
三井住友銀行本店法務部
4 債務名義について
執行可能な債務名義の取得後に限り、判決の確定を問いません。
ただし、前述のとおり、執行証書(民事執行法22条5号)は協定対象外です。
5 方法
弁護士法23条の2に基づく照会(弁護士会照会)
三井住友銀行所定の書式の提出が必要です。
6 費用
弁護士会照会の通常の手数料・郵券代のほか、三井住友銀行の所定用紙1枚につき手数料3240円が(税込)が必要です。
債権回収の実効化のため、現在、民事執行法の改正も検討されていますが、それに先立って、弁護士会照会という形で三井住友銀行における口座情報の開示が得られるようになりました。
今後の利用により、債権回収の実現可能性が高まることが期待されます。

東京都中央区銀座の「馬渕総合法律事務所」は、企業法務から不動産、労働問題、債権回収、破産など幅広い分野に対応しています。
迅速かつ的確なアドバイスで、ビジネスにおける「安心」をご提供。
東京、神奈川、埼玉、千葉を中心に、日本全国からのご相談もオンラインで承ります。
お客様のビジネスに寄り添い、法的なリスク管理と成長をサポートするパートナーとして、誠実に対応します。
まずはお気軽にお問い合わせください。